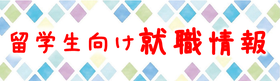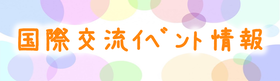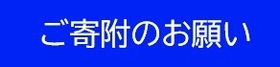The La Paz Times~ラパス便り~第1回
The La Paz Times No.1 From 04/09/2010 to 12/09/2010
今年も始まりました2010年度メキシコ海外実践教育カリキュラム。デービス滞在記でもお届けしている通り、今回はプログラムを大幅にバージョンアップ、1ヶ月UCデービスでの渡墨前語学研修を追加し、9名の学生が参加しました。9月3日にラパス直行組の6名が鳥取を出発、経由地ロサンゼルスにてUCデービス組の9名と合流、9月4日に15名の学生が無事ラパス入りしました。残暑厳しい鳥取から来た学生達もラパスの暑さには閉口。強烈な陽射しと雨期の蒸し暑さの中、カリキュラムスタートです!
| 1限目 9:00-10:30 |
2限目 10:40-12:10 |
3限目 13:10-14:40 |
4限目 14:50-16:20 |
5限目 16:30-18:00 |
|
| 9月6日(月) | 開講式 | ||||
| 9月7日(火) | スペイン語① | フィールドワーク1(地域学部:ケイツ教授) Comparative Culture: Mexico and Japan: A regional study of Differences in Culture, People, and Society |
|||
| 9月8日(水) | フィールドワーク1(地域学部:ケイツ教授) Comparative Culture: Mexico and Japan: A regional study of Differences in Culture, People, and Society |
||||
| 9月9日(木) | 国際コミュニケーション論① | スペイン語② | 日墨比較文化① | 中南米社会経済事情① | |
| 9月10日(金) | フィールドワーク1(地域学部:ケイツ教授) Comparative Culture: Mexico and Japan: A regional study of Differences in Culture, People, and Society |
||||
今週火曜日からメキシコ海外実践教育カリキュラムがスタートしました。第1日目はスペイン語の講義と地域学部キップ・ケイツ教授による「メキシコと日本の文化比較」のフィールドワークでした。文化比較ではこれからの講義の内容と最終日のプレゼンテーションに向けての班分けを行いました。メキシコのタブーや習慣、時間の感覚、価値観、15歳の誕生日についてグループに分かれての日墨比較調査を行います。この日がメキシコで行う初めての英語での授業ということもあり、皆緊張した面持ちでメモを取る姿が印象的でした。
|
|
|
フィールドワーク2日目は朝のセントロ(ダウンタウン)での調査を行いました。調査ではそれぞれの班の調査内容に沿って用意した質問があり、皆スペイン語に苦労しながら現地の人たちと話をしていました。午後は講義室に移動して午前の調査内容について各班で意見交換を行い、金曜日の小学校訪問に向けての質問の作成を行いました。メキシコ現地の学生たちが英語をスペイン語に翻訳する作業を手伝ってくれたおかげで英語でのコミュニケーションの練習にもなり、とても勉強になった1日でした。
|
|
|
第3日目は英語・スペイン語・メキシコと日本の文化比較・メキシコの社会と経済についての4つの講義が行われました。メンバーは英語での授業について行くのがやっとといった風で、講義が終わったころには当然僕を含めた全員が疲れきった顔をしていました。これからの3ヶ月間で徐々に慣れていくものだと信じたいです。
|
|
|
|
英語での講義の様子 |
比較文化の授業はUABCS学生も一緒です |
第4日目はフィールドワークの一環で、CIBNOR の近くにある小学校を訪問して文化比較のために考えたアンケートに回答してもらいました。言葉がなかなか通じなかったので最初は困っていましたが、徐々に打ち解けてくると言葉の壁を感じることもなくなって、一緒に剣玉で遊んだり彼らの名前のカタカナ表記を教えたりと、時間がたつのも忘れていました。最後には日本とメキシコの有名な歌をお互いに歌ってお別れをしました。 午後は小学生が回答してくれたアンケートの翻訳作業と集計です。誤字を気にせず力いっぱい回答してくれたアンケート用紙はとても読み応えのあるものでした。また、土曜日にはセントロの教会で行われている、青年団達の教会学校にて意見交換会、日曜日にはミサを見学し、メキシコの宗教に関する知識を習得することも出来ました。メンバーはキリスト教に関して意外にも知らないことが多く、皆真剣に聞き入っていました。(上谷)
|
|
|
|
お礼に日本の歌をプレゼント |
折り紙は現地小学校でも大人気 |
メキシコについて
ラパスで暮らしはじめてまだ一週間ほどですが、まずは気候について紹介します。乾燥地で雨の少ない地域なので、今のところ雨は降っておらず、ほとんど毎日晴れています。日々の生活を送る中でもなるべく水の無駄遣いをしないように心掛けています。昼間は日差しが強くすごく暑いのに対し、朝晩は涼しくなり半袖では肌寒く感じる時もあります。1日の寒暖の差が大きいです。

少し外に出歩くと日本と違うところがすぐに見つかります。歩行者用の信号がありません。車が来てないことを確認して渡っていますが、安心して渡ることができず怖いです。ただ止まって譲ってくれる車はたくさんいます。メキシコには良い人が多いのでしょうか。単純にそうは言えませんが、とりあえず歩道を歩いている外国人にクラクションをならして手を振ってきたり、何か叫んできたりするような陽気な人が多いのは確かです。さらにメキシコ人は赤と緑が好きです。町を歩くと壁や車、衣服など多くのところに赤と緑が見られます。考えてみれば、赤と緑はメキシコの国旗に含まれている色です。国旗を上に挿している車や路上で国旗を売っている人もたくさんいます。これは今年メキシコが独立200周年だからかもしれませんが…。

最後に物価について話します。通貨はペソです。ペソを約8倍した値が日本円に相当します。1ペソ=8円くらい。大体のものが日本より安く手に入りますが、見たところ電子機器や衣類はさほど変わりはないようです。食材は安いので普通に暮らしていく上では日本よりお金はかからないでしょう。ほぼ毎日きちんと自炊して生活しています。(糟谷)
コラム
“¡Hola!”と、温かいあいさつで迎えられ、私たちのメキシコでの生活がいよいよ始まりました。ここでは講義やフィールドワークだけでは得られない、メキシコの文化や習慣、伝統を垣間見ることができます。たとえば、メキシコにはsiestaという「昼寝、またはスペイン語を中心に生活習慣として認められる昼寝を含む長時間の休憩(13:00~16:00)」があります。“睡眠過多ではないか?”と心配していましたが、この文化のあるところでは、「昼食と同様夕食も日本より遅く、したがって就寝時刻も遅い。しかし、朝は早い。よって、siestaなしのライフスタイルと大差はない」ようです。 また、スーパーに行くため通りを歩いていても、私たちのような外国人観光客がめずらしいらしく、クラクションを鳴らされたり、チップをもらうために道路の真ん中でfireactionをする人を見かけたりもしました。 しかし、そんな中でもバスの中からふと見る景色が新鮮で美しかったり、メキシコ人やここでお世話していただく方々がとても親切で、とても恵まれた環境にいると思います。また、ここに到着した初日から、同じ年くらいのメキシコ人の友達が宿舎まで駆けつけてきてくれて、彼らからもメキシコの様々な言語や歴史、流行を教えてもらっています。まだまだ初めてのメキシコ、初めての海外、初めてのメンバーにみんな緊張していますが、早くこの生活になじんで、もっともっとメキシコを感じて、この土地からいろいろなことを吸収したいと思います。私たち15人、一人一人が、得意な分野も、ここに来た目的も違うと思いますが、みんなで助け合い、切磋琢磨して成長できたらと思います。これから三ヶ月、何が起こるかお楽しみに♪ (金剛)
PHOTOS
|
|
←ロサンゼルス~ラパス間の飛行機はプロペラの小型飛行機!ゲートから一度地上に降ろされ、タラップを上がって乗り込みます。 |
|
|
|
|
↑ 初日、UABCSコンベンションセンターにて行われた開講式の様子。開講式後の立食会で UABCS学生と一緒に。 |
|
|
|
←メキシコ宗教に関する調査のため教会 訪問。15歳の誕生日(キンセ・ア ニョ) のお祝いミサに遭遇 (ピンクのドレスの女の子が主役)
|