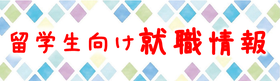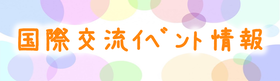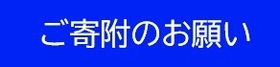フィリピン英語イマージョンプログラム
令和6年度参加学生
農学部1年生
私がこのプログラムに参加したいと思ったのは、留学説明会で見たバギオ市の家々が山一面に広がっている様子に写真ながらに圧倒され、実際にこの目で見てみたいと思ったからだ。また、鳥取大学初の留学プログラムで、一人ではなかなか行けないフィリピンの北部に行き現地で英語をしゃべりながら、様々な体験をするという点に惹かれぜひ参加したいと思った。
私にとって、初海外のフィリピンでは本当に濃い日々で充実した13日間となった。マニラに着いても、本当に自分が海外に飛び立ったのか実感が湧かなかったが、空港からバギオ市にバスで移動する時、マニラ市内を見て、ビルが立ち並ぶ近代的なビジネス街とその手前の生活感あふれる住居のギャップが、海外に来たんだなと感じるとともに、日本ではあまり感じなかった治安の悪さを実感し、バスの中がどれほど安全なのかが身に染みた。
そうして始まったフィリピン生活は、初めからカルチャーショックの連発だった。最初はトイレットペーパーが流せなかったことだ。時には便座がなく、紙自体が置かれて無いことにかなり驚いた。次に影響を受けたのは、水道水の使い方についてだ。飲料水として飲むことはかなり危険で、水道水でうがいすることや歯ブラシを洗うことでさえ気を付けた。
初日の活動ではベンゲット州立大学の校内を案内してもらい、どういった学部があり何を学んでいるのか、また大学の施設を見学し、夜にはwelcome dinnerが開かれた。そこで私たち日本人学生は、ソーラン節とドラえもんの歌を日本の文化として披露した。BSUの学生は伝統ダンスと英語の曲を披露してくれた。その後の食事会で、私は最初の壁にぶつかった。それは、積極的に行動できない自分だ。特に感じたのは、他人の英語力と自分の英語力を比べ、文法が正しく使えているかなど、英語を話すことに抵抗をもち、失敗を恐れていたことだ。その時、積極的に会話している学生をまるで傍観者のように見ていた。その夜は、話す機会はたくさんあるにもかかわらず、自発的に行動できなかった自分が、日本にいるときと全く変わっていないと感じ、非常に後悔した。
このイマージョンプログラムでの私の目的は、日本を出てみて海外がどんなものなのか自分の目で見て観察し視野を広げるということと、英語は好きでも、間違いを恐れて英語を話そうとしない自分を変えることだ。初日の出来事では、目的を再認識することとなり、その日できなかったこと、話したかったことをノートに書きだし、振り返ることで、次の日に生かせるようになった。
今回のプログラムには、ベンゲット州の高校と大学に行って日本語や日本の文化を紹介するという活動があった。日本語を学んでくれている現地の学生は、すごく意欲があり、どういう風に話したら理解してくれるのか、英語も話しながら身振り手振りで、表情豊かに話しコミュニケーションをとった。日本語を話すときは、口を大きく動かして表情を変えてといった感じで全体を使って話すことはあまりなかったため、英語を話すことが本当に楽しかった。また、現地の学生と話していて、驚き気付いたことがある。それは、教科書を使って語学を学んでいないということだ。教科書は使わずに、その言語の歌を聴くことや、実際に話すことで学んでいると聞いてかなり衝撃を受けた。私は、語学を教科書無しで学んだことが無かった。英語は小学生の頃から今まで継続しているのに、なぜ英語力が向上しないのかと考えた時に、教科書の文章を読むことや聞くことが多く、しゃべる機会が圧倒的に少ないと気づいた。もちろん、読むことも大事だが、話すことが語学力向上には直結しているように感じた。
そして迎えたマニラ視察では、バギオで過ごした日々とはかなり異なる刺激的な体験となった。バギオでは一昔前の街に来たような感覚だったが、マニラで宿泊したマカティ市は高層ビルが立ち並ぶビジネス街で日本とほぼ変わらない様子に驚いた。その一方で、世界遺産や博物館を視察するため、マカティから出ると、人々の来ている服や食べ物など、生活の様子が一変し、バスの中から見るだけでもかなり印象的だった。また、サンチャゴ要塞地の視察やアヤラ博物館では、日本が昔フィリピンに対してどのようなことを行ってきたのか知って、歴史に対して無知な自分が恥ずかしく思えた。
フィリピンイマージョンプログラムでは、英語を使いながら毎日のスケジュールに没頭し、現地の人々や環境と適合し続ける13日間となった。この13日間を通して、語学の面では、英語が出てこない時は英語を話す以外の方法でコミュニケーションをとることが可能だったが、単語力やリスニング力がもう少しあれば、曖昧な場面もはっきり理解することができ、より会話の質が上がると感じた。生活面では、食事、トイレや水の安全性、電球の暗さなど、日本ではあまり考えていなかったことを意識し、適応しながらも、日本のインフラが整っていることや、技術力の高さを実感した13日間だった。今回のプログラムを終えて、今後は英語力の向上に加え、国の歴史を学び直したいと思う。